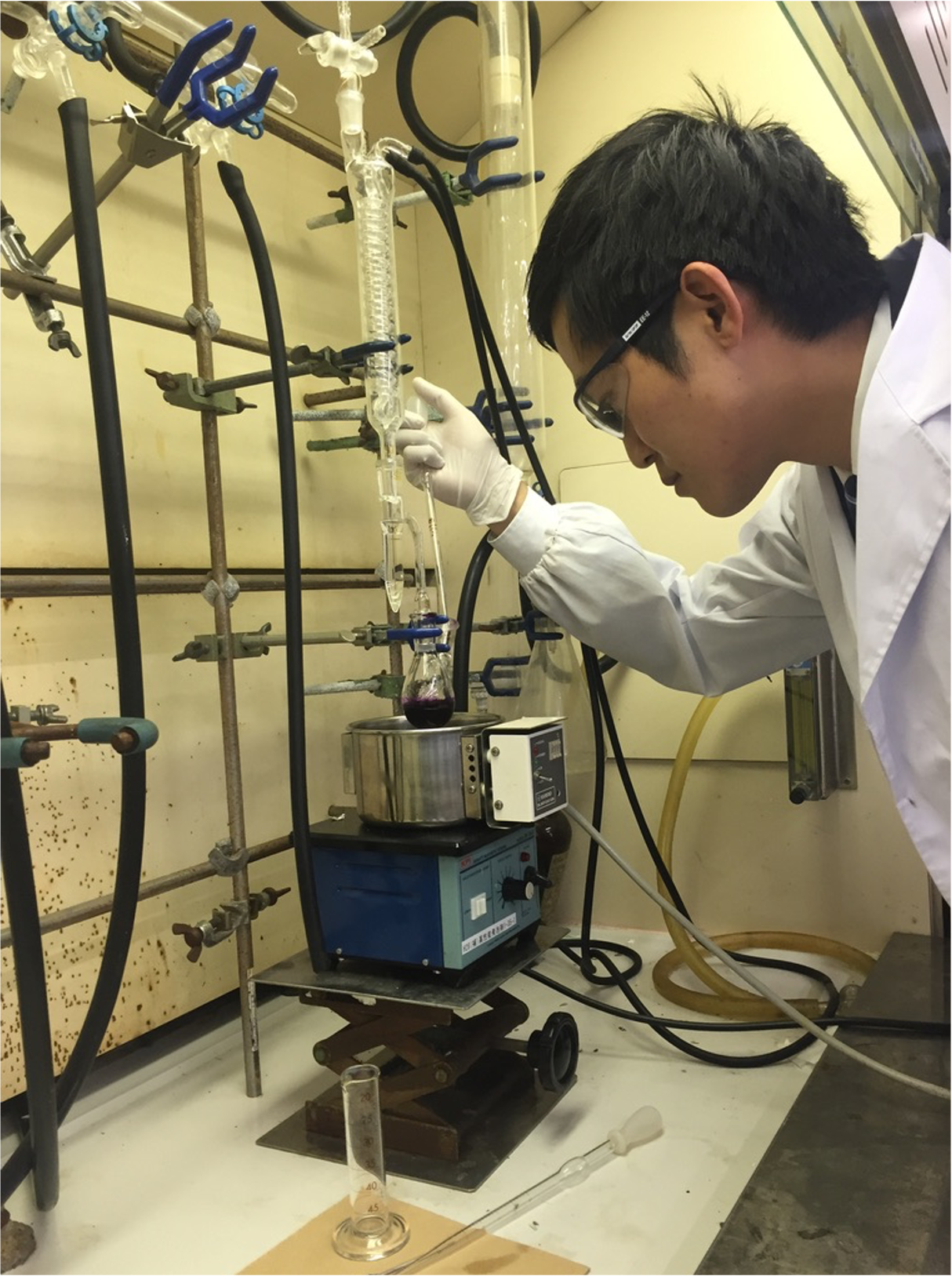今回は2025年2月に実施された、第5回アトツギ甲子園でグランプリを勝ち取った、株式会社あしだの芦田さんです!
今までの軌跡から伺っていきます!芦田さんの歩みを是非ご覧ください!
株式会社あしだ
芦田拓弘さん
エネルギー業界での海外勤務を経て、林業を営む株式会社あしだのアトツギとして家業に復帰。伝統的な林業にITやデジタル技術を積極的に取り入れ、地域通貨アプリ「EcoPay」を開発。地域での決済を森林保全に還元する仕組みを構築した。持続可能な森林活用を推進しながら、林業の新たな可能性を追求し、業界に革新的な挑戦を続けている。
ゴードン:
今回はアトツギファーストの特別企画として、先日の第5回アトツギ甲子園でグランプリを獲得された株式会社あしだの芦田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします!
芦田さん:
よろしくお願いします。
サッカーに一途な学生時代
ゴードン:
では、芦田さんが家業に入るまでの話や、甲子園で優勝するまでの道のりを順番に聞いていきたいと思います。まずは、子供の頃ってどんな少年だったんですか?
芦田さん:
森に囲まれた町に生まれて、ずっとサッカーをしてました。将来の夢はプロサッカー選手で、サッカーのために中学受験をして、中学から祖母と二人暮らしで地元を離れました。そこからは勉強しながらサッカーを続ける感じでしたね。
ゴードン:
サッカー以外に好きだったものとかあります?
芦田さん:
いや、サッカーしかしなかったですね(笑)。休み時間には次のサッカーメニューを考えて、チャイムが鳴ったらすぐボール持ってみんなでサッカー。学校が終わったら帰り道も走るトレーニングしてました。「サッカーがなかったら俺は生きる価値ない」みたいな感じで、「努力したら神様が見てくれる」って盲目的に信じてました。挫折もしましたけどね。
ゴードン:
挫折ってどんなものだったんですか?
芦田さん:
結局、私がダメだったのは効率的に練習できなかったことですね。自分のやってることが本当に正しいのか考えずに、同じメニューをただ数こなす練習をずっとしてたから、最終的にうまくいかなかったんです。
ゴードン:
それって先生の影響で「とにかく根性でやれ」みたいな感じだったんですか?
芦田さん:
そうですね。地元のサッカーの師匠がめっちゃ熱血タイプの人で(笑)。ただ、その時期の癖は今も抜けてなくて、何かあるとまず手を動かしてガーッとやるみたいな。周りから「もうちょっと冷静になれよ」って言われることもありますけど、それが私の特性でもありますね。
ゴードン:
でもそれがあるからこそ爆発力が出るところもありますよね。今の芦田さんの根っこを作ってるとも言えるかも。
芦田さん: そうですね。今ちょうど0→1フェーズの事業では。周りのメンバーに助けてもらいながら進められています。
ゴードン:
中高、大学でもサッカーを続けられたんですか?
芦田さん:
大学はサッカーじゃなくて、フットサル部に入ってました。
ゴードン:
なるほど。小さい頃の家業の印象ってどんな感じでした?
芦田さん:
家業が林業なので、伐採のイメージがありました。小学4年生の頃、ちょうど20年前ですが、「石油があと50年で枯渇する」とか、「アマゾンで焼畑農業」「海外で違法大量伐採」「CO2で地球温暖化」みたいなことが叫ばれ始めた時期です。うちは林業で伐採するため、環境破壊してるみたいで、後ろめたい気持ちがありました。
ゴードン:
そういう時にお父さんお母さんと家業について話したりしました?
芦田さん:
自宅の目の前が会社だったんで、トラックの出入りとかは日常の光景でした。でも実は林業って植林から始まる60年かけて森林を育てる意義のある仕事なんです。林業が森林によるCO2吸収(脱炭素)や災害防止に貢献しています。そういう認識を変えていけるような事業を展開していきたいなって今は思います。
ゴードン:
当時はあまり良いイメージはなかったんですね。小さい頃から「お前は跡取りだ」みたいな話はあったんですか?
芦田さん:
特になかったですね。「お前ら好きなことをしろ」っていう方針で。兄弟2人とも男なんですけど、「家のこと考えなくていいから、自分のやりたいことをしろ」って感じでした。
ゴードン:
家業を手伝ったりすることはありました?
芦田さん:
たまに丸太をトラックに積んで、親父の話し相手でトラックに乗ることはありました。市場の自販機でジュース買ってもらうのが楽しみで。「力水」っていう飲み物があって、それが好きでついていったりもしました。でも長時間親父がずっと話してるから「まだかな、早く帰りたいな」って思ってました(笑)。
ゴードン:
そういう時に見る光景って記憶に残りますよね。中高生や大学生になって進路を考える時期に、家業の話は出なかったんですか?
芦田さん:
中学からはサッカーのために家を出たので、ほとんど家にいなかったんですよ。中学・高校は祖母と二人暮らし。家業とは離れた生活をしてました。
「ノーベル賞への憧れから産業の最前線へ」── 化学者からプラントエンジニアの道
ゴードン:
学校卒業後は家業に入らず、どういうところに就職されたんですか?
芦田さん:
高校でサッカーをやめて一度浪人して、プロサッカー選手の夢がなくなったから「次は何をしよう」って。そのとき化学に興味があって、化学の大学・大学院に進みました。
ゴードン:
なんで化学に興味を持ったんですか?
芦田さん:
なにかで社会貢献をしたかったんです。ちょうど日本人のノーベル賞受賞者がたくさん出てた時期で、「新しい発見をしたら世の中に貢献できるし、魅力的だな」って思いました。
ゴードン:
大学ではどういった研究をされてたんですか?
芦田さん:
有機化学を研究してました。新しい化合物の構造式を自分で設計して、その新物質を使って太陽光電池の研究をしてたんです。今でいうペロブスカイトみたいな折り曲げられる太陽電池に関わるエネルギー系の研究テーマでした。
ゴードン:
その分野を選んだ理由はあるんですか?
芦田さん:
基礎研究だけでなく実用的なものを作って社会貢献したいという思いがありました。その思いから就職はエネルギー系のプラントエンジニアになりました。地図に載る規模の大きいことがしたいと思いました。
ゴードン:
石油プラントの会社では主にどんなことをされてたんですか?
芦田さん:
原油からガソリンやLNGを生成する工場を建設する仕事です。大きいプロジェクトだと工場の広さが縦横3キロメートルにもなるような規模。最後のプロジェクトはコロナの時期で、予定してた中国行きが中止になって、国家プロジェクトのコロナワクチン製造工場の建設に携わることになったんです。そこでメインポジションで引き渡しまでプロジェクトを担当させてもらいました。
ゴードン:
この仕事を通して学んだことや、やり遂げたと感じる部分はどこですか?
芦田さん:
2つあります。1つはプラントエンジニアの会社の面白いところで、プロジェクトごとに組織ができるんです。いろんな部署から人を集めてプロジェクトマネージャーを中心に組織が作られるんですけど、その組織づくりがめちゃくちゃ勉強になりました。プロジェクトマネージャーがどう判断して人をマネジメントしていくか、その熱量も含めて背中で見てきたので、今もすごく活きてます。
もう1つはお客さんへの姿勢です。工場って納期が決まってて、1日でも遅れると会社が数億円の違約金を払う契約になってるんです。だから納期は絶対。でも、必ずトラブルはあります。そういう時にお客さんと親身になって最後までやり切ることで「この会社と仕事してよかった」と思ってもらえ、次の仕事も任せてもらえる。その「物を納める」っていう向き合い方をすごく勉強しました。
ゴードン:
プロジェクトマネージャーとして一番大事なことって何だと思います?
芦田さん:
私はマネージャーじゃなかったんですけど、マネージャーの後ろについて仕事をして、いろんなタイプのマネージャーを見てきました。ある人は淡々とこなしながらも最前線で全てを指揮するタイプ。プラント建設では専門部署以外の様々な知識が求められます。互いの専門性を尊重しながら最前線で旗振りをしていました。
別のタイプはシステマティックに組織を作ってプロジェクトを進める人。また別の人は若くても能力のある人を要所要所に配置して、彼らをモチベートするのが上手い。責任は自分が取りつつも裁量権を与えて、のびのびと仕事をさせてくれる。実は本当の意味で裁量権を与えるのは難しいことなんですが、責任重大なプロジェクトでもそれをやってる人がいました。「人でプロジェクトが回る」というタイプですね。
システマティックに回すタイプと人で回すタイプ、いろんなマネージャーの背中を見られたのはすごく勉強になりました。
林業への可能性と家業へのコミット── アトツギの始まり
ゴードン:
いろんなやり方があって、自分に合うやり方を選ぶべきだという学びにもなったんですね。そういう経験を経て、家業に戻られることになったんですか?
芦田さん:
そうですね。タイミングよく5年目の時に一通り経験させてもらって、自分が一から事業をしていきたいと思って前の会社を離れました。
ゴードン:
お父様やお母様から「戻ってきてほしい」と言われたわけではなく、芦田さん自身のやりたい気持ちからだったんですか?
芦田さん:
そうです。正直、やり切ったというのが本音です。最後のコロナワクチン工場のプロジェクトでやり切って、経験を積んだのでめちゃくちゃ自信がありました。ゼロから全部独学で学んで、専門外のことも全てやって、お客さんにも認めてもらえた。その時はすごい勢いがあって「今なら何でもできる」という自信がありました。
ただ5年目ってまだ若手で、自分がもっと最前線で自分の責任でやりたいという思いが強くなりました。また次のプロジェクトでインドネシアに2年間赴任する予定もあったので「今逃したらダメだな」と思いました。
正直に言うと「アトツギだから林業をやった」というだけじゃなくて、「何でもできる」という自信と、社会貢献したいという思いから林業を選びました。
大きな理由としては、プラントの仕事は何万人もの人が関わる規模で、ミスを防ぐシステムづくりが求められます。人間の思考が入るとミスが生じるので、できるだけ人が関わらないマネジメントが理想とされる世界でした。ある意味、人はロボットのような存在になってしまう。
ちょうど将棋の羽生さんがAIに負けるニュースもあって、人間がどんどん機械やAIに置き換わっていく感じがしました。逆に「人が人として活きる仕事は何か」と考えた時に、人がやりがいを持って働く時のエネルギーはとんでもないと実感していたんです。
そこで「人が自分の人生をかけてやりがいを感じられる仕事は何か」と考えたら「第一次産業だな」と。特に林業は自然の谷や川など様々な条件があって、AIが最も置き換わりにくい分野です。人という要素は絶対に必要で、最終的には第一次産業にみんながやりがいを持って働ける場所を作れるんじゃないかと思い、覚悟を決めて林業のアトツギとなりました。
ゴードン:
子供の頃はあまり良い印象がなかったと言ってましたが、戻る時に葛藤はなかったですか?
芦田さん:
葛藤はめちゃくちゃありました。現場仕事なので、30歳の私の体が動くのかという不安や、従業員に受け入れられるかという心配もありました。現場は技術職なので、その辺はすごく不安でしたが、ゼロから勉強するつもりでした。
ゴードン:
ご両親は戻ってくることについてどう反応されました?
芦田さん:
あまり良くは思ってなかったです。会社に勤めている方がいいんじゃないかという感じで。親父が会社を経営してきて苦労を知っているから、息子も苦労するだろうと思ってたと思います。
うちの会社の特徴的なところは、従業員15名が全て現場職員です。そのため親父が現場も計画もしていて。その辺を逆に助けたいという思いはありましたが、現場をしながら夜はずっとパソコン作業する状態が続いていたので、それは心配でした。
ゴードン:
お父さんとは対話は多いですか?
芦田さん:
かなりします。
ゴードン:
後継者として入るのと、自分がこの会社をやっていくんだというスイッチが入るタイミングって結構ずれていると思うんですが、スイッチが入った瞬間はありました?
芦田さん:
アトツギとしては暫定段階で、現在、親父が社長です。でも自分事として会社を考え始めた瞬間としては、外的要因が大きかったです。
うちの会社は現場仕事で天候に左右されます。雨の日や雪の日は休みで、でも従業員からすればもっと働きたい。林業は現場仕事で、怪我でもしたら大変。普通なら別の部署での仕事もあるはずですが、うちは林業しかないから雨の日は仕事できない。
持続的に会社を継続するためには、この林業一本足打法から脱却しないといけない。福利厚生を改善して休みも増やさないといけない。今風じゃないので変えていかなければと思い、従業員のために新しい事業も始めました。
ゴードン:
自分事になっていく感覚ですね。お父さんの会社に入っても自分の会社じゃないという感覚から、自分がこの会社をやっていくという自分事になる。この変化を感じているアトツギさんはすごく強いと思います。それはいつ頃気づいたんですか?
芦田さん:
入社して現場に入って半年くらいですね。林業は特殊で、私は現場作業をしながら森林の整備計画も担当することになったんです。森林をどう整備していくかという計画を国に提出する経営計画という業務を、私が入って初めて担当しました。
この計画作りを通じて考え始めたのが大きかった。今までうちの会社は依頼毎の下請け体質でやってきたので、その状況を変えないと会社の存続が危うい。今は親父の属人的な経営で成り立っている会社なので、私が将来を見据えて引き継いでいかないとという思いが半年くらいで芽生えました。
ゴードン:
危機感から来る部分が大きかったんですね。
芦田さん:
危機感はありますね。重機が故障すると数百万円の修理費がかかるし、操作ミスで危険なことも起こりうる。危険と隣り合わせの仕事なので、常にそういう思いはあります。
ゴードン:
そういったバックグラウンドを経て、危機感を持って雨や雪の日でも働ける仕事を模索されたわけですね。今回のアトツギ甲子園で発表された木材流通システムを考えられたきっかけは何だったんですか?
---------------------------------------------
ご自身と家業を掛け合わせながら、課題解決や新規事業に取り組まれている芦田さん・・・。4分のピッチでは語ることができない、これまでの過程が面白く聞き入ってしまいました。
次回はいよいよ、そんな芦田さんの新規事業についてお伺いし、アトツギ甲子園の裏側に迫っていきます!
(次回は4/1公開予定)

![ナラティブインタビュー前編: 林業の可能性を信じ、未来を作るアトツギ(芦田さん)[1]](https://image.osiro.it/pass/main_images/465406/images/original/29807CB0-FD7A-4798-9165-A8C78648E3EC_2.JPG?1742913600)